 |
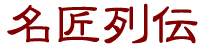 |
|
ハンス・シュミット・イッセルシュテットHans Schmidt Isserstedt(1900-1973) |
 |
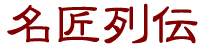 |
|
ハンス・シュミット・イッセルシュテットHans Schmidt Isserstedt(1900-1973) |
|
|
|
| シュミット・イッセルシュテット小伝
<生い立ち> 逆にそのためしばしば誤って呼ばれることとなり、「ハンス・メッサーシュミット」とアナウンスしたラジオ局すらあったとか。 シュミット家はビール醸造所を営んでいたが、父はピアノを、母は歌をよくする音楽的な家庭だった。醸造所併設のカフェで演奏していた楽士のヴァイオリンに惹かれ、家庭で室内楽を演奏したり(モーツァルト;クラリネット五重奏曲に魅了されたという)、アマチュア・オーケストラのコンサートマスターをしたりしながら勉学を続けた。 <指揮者として> <北ドイツ放送響> 彼の非ナチ問題は、このときに質問票に回答したことで決着したとのことである。戦時中に就いていたポストを考えると、例えばハンス・クナッパーツブッシュの重い処分などに比べて恵まれすぎているように思うが、これはミュンヘンを占領したアメリカ軍と北西部を占領したイギリス軍との姿勢の違いによるのかもしれない。 「ベルリン・フィルとウィーン・フィルを交配した弦楽器と、コンセルトヘボウとフィラデルフィアが結婚した管楽器」をめざし、シュミット・イッセルシュテットは各地の捕虜収容所を駆け回って楽員のオーディションを行った。またドイツ各地から優秀な楽員が集まり、中でもベルリン・フィルのコンサートマスターであったエーリヒ・レーンを得たことは有名である。 ベートーヴェン;「エグモント」序曲 というもの。 この間、1956年に放送局の名称変更に伴い、「北西ドイツ放送交響楽団」から「北ドイツ放送交響楽団」にオーケストラの名前も変わっている。 1955年から1964年まで、カール・フォン・ガラグリの後を襲ってストックホルム・フィルの首席指揮者を勤め、ここでも現代音楽を盛んに演奏した。 <来日公演>
読売日響には1970年、ベートーヴェン生誕200年を期して再度客演し、交響曲第9番やミサ・ソレムニスを指揮した。
ユーモアに溢れた人柄で、「カラヤンをどう思うか?」と尋ねられて、「ユーモアのセンスに欠けるね」と評したという。また、大町陽一郎氏の回想によれば、北ドイツ放送響に客演したストラヴィンスキーが楽譜をめくるたびに拍子が危なくなる様子や、リハーサルでベームがオーケストラに注文を付ける様子の口真似・振り真似は爆笑ものだったそうだ。 <録音活動>
戦後も録音活動は続けているが、あまり恵まれたものではなかったところ、1958〜59年、ヴィルヘルム・バックハウス独奏によるベートーヴェン;ピアノ協奏曲全集でウィーン・フィルを指揮して共演したことと、1965〜69年に同じ作曲家とオーケストラの交響曲全集を録音したことで、一躍、レコード愛好家に名前を知られることとなった。 この抜擢については、子息エーリヒ・シュミット(エリック・スミス)が英DECCAのプロデューサーであった関係と噂され、また録音現場を実見した人は、「オーケストラのほうは、ただ黙々と、指揮と録音技師の指示に従う、といった態度に見えました。」と語っている。しかし、結果として生まれた音盤は、1960年代のウィーン・フィルの良さを最も素直に出したものとして、今なお評価が高い。 最も愛したモーツァルトの音楽に散発的な録音しかないのは残念だが、バンベルク響との交響曲第31・35番(独ACANTA)、ロンドン響との交響曲第39・41番(米Mercury)、北ドイツ放送響 ほかとの歌劇「恋の花つくり」(蘭Philips)等が主なものである。 珍品としてはラヴェル;ピアノ協奏曲(モニク・アース、独DGG)、ヴェルディ;歌劇「椿姫」抜粋(マリア・シュターダー、エルンスト・ヘフリガー他、独DGG)等が面白い。 シュミット・イッセルシュテットは、ブラームスの音楽に特別な親しみを覚えていたようである。
そのブラームス演奏には、彼の剛直な面がよくあらわれている。ジネット・ヌヴーとの伝説的なヴァイオリン協奏曲や、ライヴ録音の交響曲第4番が代表的な名演であろう。後者は彼の死の1週間前、1973年5月21日に行われた手兵北ドイツ放送響との最後の演奏会の記録である。当日はオール・ブラームス・プロで、 ピアノ協奏曲第1番(独奏;ハンス・リヒター・ハーザー) というものであった。 |
|
|
|
|
関連リンク集
|
 |
|
|
|
| |
|
|
名匠列伝へ戻る 指揮列伝へ戻る
斉諧生へ御意見・御感想をお寄せください。 |
|