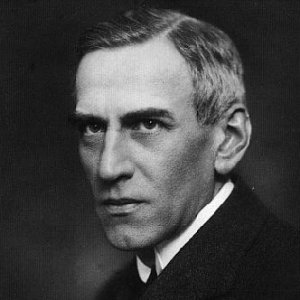ステーンハンマル小伝<時代背景の中の作曲家>北欧においては、今でこそ、デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデンという5カ国が平和裡に共存しているが、この体制が確立したのは近々、1944年にアイスランドがデンマークから独立してからのことである。 ステーンハンマルが生れた頃、独立国家であったのはデンマークとスウェーデンのみであり、アイスランドはデンマーク、フィンランドはロシア、ノルウェーはスウェーデンの、それぞれ自治領ないし保護国であった。 この時代の北欧は、経済的には産業革命が、国内政治においては民主主義的議会政治への改革が進む一方、対外的にはドイツ帝国や帝政ロシアの勢力拡張の中で圧迫を蒙ると同時に、各国ごとの民族的自覚が高揚した時期に当たる。 ステーンハンマルの、そしてグリーグ(1843-1907 ノルウェー)、シベリウス(1865-1957 フィンランド)やニルセン(1865-1931 デンマーク)らの音楽を考える上では、こうした時代背景を知っておくことは無駄でないと思う。 斉諧生按ずるに、彼らの音楽は、いずれも国や時代を超えた芸術としての価値を有するが、同時代にあっては、彼らは、いずれも勃興する民族国家の文化的アイデンティティを担っていたといえるだろう。 長くスウェーデン領であったフィンランドでは、スウェーデン語が公用語とされていた。19世紀中葉、フィンランドの文化人は、「フィンランド人には2つの敵がいる。政治的な敵としてのロシア帝国、文化的な敵としてのスウェーデン語」と唱え、民族叙事詩『カレワラ』の収集・出版などを通じて、フィンランド語が優れた文化的遺産を有すること、ひいてはフィンランド人の民族文化への自信を鼓吹することに努めた。 また、デンマークとスウェーデンの角逐の舞台となったノルウェーにおいては、「ノルウェーこそ北方ゲルマン人の第一の子孫であり、北欧文化の最も栄光ある担い手である」とのプロパガンダが行われ、ノルウェー語からデンマーク語の影響を排する文化運動も実施された。 もちろん、北欧各国間の対立・背反のみに目を向けるのは一方的である。政治的スカンジナヴィア主義といわれる、北方民族の大同団結をめざす潮流もあり、現実政治の上でも、第一次世界大戦におけるスウェーデン・ノルウェー・デンマークの相互協力による中立の維持といった成果も見られたのだから。
<生い立ち>ステーンハンマルは、1871年2月7日ストックホルム生れ。厳格なプロテスタントの信仰を持つ家庭で育てられた。彼はこれに強く反発し、はっきりした信仰は持たず、宗教曲は1曲も作らなかった。とはいえ、一方で倫理的な生き方を強く志向したのは、その影響であろう。 父親ペール・ウルリク・ステーンハンマルは、建築家であるとともに作曲家でもあり、数曲のオラトリオや歌曲が残っている。母エヴァは貴族の家柄の出で、やはり音楽的素養があった。また、叔父夫婦は歌手だったし、音楽的な環境で育ったと考えてよい。 9歳でモーツァルト風のピアノ・ソナタを作曲するなど、「神童」的な育ち方をしたが、1887年、16歳の時に真剣に音楽に打ち込むことを始め、クララ・シューマンの弟子であるリシャード・アンデルソンにピアノを学び、翌年からは作曲をエーミル・シェーグレンに学んだ。 初期の作品にはシューマネスクな旋律が美しい歌曲や、和声に北欧特有の透明感のある合唱曲が多い。いずれも内輪の音楽会で演奏されたものと思われ、作曲家自身もあまり重きを置かなかったようで、出版されなかったものも多い。しかし、中では「3つの無伴奏合唱曲」は、1939年の蘇演・出版以後、合唱団の重要なレパートリーになっている。
<ドイツ留学>1892〜93年にベルリンへ留学し、ハインリヒ・バルト(ハンス・フォン・ビューローの弟子、ヨアヒムの盟友)にピアノを学んだ。また帰国後も、しばしばベルリンを訪れている。 この間に、ステーンハンマルはワーグナーの音楽、とりわけ『ニーベルングの指環』に魅了され、自身のオペラ「ソルハウグでの宴」・「ティルフィング」は、いずれもワーグナー風のものであったらしい。 シベリウスもベルリンに留学しているが(1890-)、この時期、北欧を脅かしているロシアに、対抗する勢力としてのドイツに対する友好的感情が、北欧各国で一般的であったことと無関係ではないだろう。
<演奏活動>留学前後から、ピアニストとして活発な演奏活動を始めている。得意にしたのはベートーヴェン、ブラームスあたりで、本格的デビューは、ブラームス;ピアノ協奏曲第1番だった。また、ベートーヴェンのソナタの大半をレパートリーにしており、「ソナタ第30番・第31番・ディアベリ変奏曲」というプログラムもよく組んだとか。 室内楽も熱心に手がけ、ヴァイオリニストのトゥール・アーウリン(1866〜1914)と彼の四重奏団とは約1,000回共演したという。 1890年代の終りごろから指揮者としても活動を始めた。特に、ブルックナーとニルセンの紹介に力を尽くしたという。
<前期の作曲活動>この時期の代表作はピアノ協奏曲第1番で、自身の独奏で、R・シュトラウス指揮ベルリン国立歌劇場管やハンス・リヒター指揮ハレ管、カール・ムックやフェリックス・ワインガルトナーらとも共演している。ブラームス風のリリカルな曲で、それはそれとして美しいが、独自の個性には乏しい嫌いがあり、ステーンハンマル自身も、1908年以降は演奏しなくなった。 また、この時期のスウェーデンでは詩人が多く活躍しており、彼らとの交遊から、多くの歌曲が生まれている。
<作曲家としての転機> 1903年に完成したヘ長調交響曲は、同年末の初演も成功し、マンチェスターでハレ管を指揮していたハンス・リヒターに総譜を送ったりもしていた。ところが、その直後にシベリウス;交響曲第2番の演奏に接して大いに感動するとともに衝撃を受けたステーンハンマルは、自作の交響曲を引っ込めてしまう。まるで「牧歌的なブルックナー」でしかなく、改訂を必要とする、というのである。 実際、よく似ている。アンダンテ楽章など、そこかしこに聴き覚えのあるフレーズが… 実際には改訂に着手することはなく、彼はヘ長調交響曲には作品番号を付さず、「第1番」という言い方もしなかった。後にト短調交響曲が完成してからは、それを「交響曲」とのみ呼んだのである。 ちょうど、この時期は作曲家の内面の転機に当たっていた。彼は妻への手紙の中で「今年、私は、審美的な理想が間違っていることに気づいた。私の意思だけが私の魂を救うのであり、世界の美は私を助けてはくれない。」と述べている。
<名作「スヴァーリエ」の誕生> 一方、この時期はスウェーデンにとっても大きな転機であった。ノルウェーがスウェーデンからの完全独立を求める動きを強めたからである。 この年、ステーンハンマルは、ヴェルナー・フォン・ヘイデンスタムの愛国詩「ひとつの民族」(1899)に付曲したカンタータを作った。初演は大成功をおさめ、繰返し上演されるとともに第2曲「スヴァーリエ(スウェーデン)」と第3曲「市民の歌」の演奏に当たっては聴衆が起立する習慣まで生れたという。 こう書くと何やら国粋主義かミリタリズムの匂いが漂うが、カンタータの初演は12月であったから、既に分離協定の批准も完了しており、むしろスウェーデン人の統合を呼びかけた曲であると考えたい。
<指揮者としての活動> 1907年秋に創設間もないヨェーテボリ響の音楽監督兼指揮者に就任し、1923年までその地位にあった。 ニルセン、シベリウスとは個人的にも親交があり、シベリウスは交響曲第6番をステーンハンマルに献じた。 その後ストックホルムに戻り、1923〜25年にはストックホルム歌劇場の音楽監督を務めた。
<創作活動のピーク>ヨェーテボリ響在任の前後は、指揮者として多忙であった上に、創作活動の上でもピークといえる時期であった。 1906年秋から1907年夏まで、ステーンハンマルはイタリアへ赴き、フィレンツェに滞在した。南国の風物は、創造意欲へのこの上ない刺激であったらしく、代表作となる「管弦楽のためのセレナード」に着手したほか、ピアノ協奏曲第2番の完成等の成果が生まれた。 彼はフィレンツェにもっと住んでいたかったらしいが、経済的・家庭上の事情で、ヨェーテボリのポストを受けざるを得なかったとか。 1910年ヨェーテボリ響でニルセン;交響曲第1番(1892)を指揮したことが刺激となって、新たな交響曲を構想するようになり、1911年、旅行先のイタリア・ボルゲーゼ荘で着手、1915年に完成したのが、ト短調交響曲(第2番)である。 更に1919年には「管弦楽のためのセレナード」を改訂、1921年には交響カンタータ「歌」が一連の傑作群の掉尾を飾った。
<晩年の活動>1920年頃からは劇音楽に興味を持ち、ヨェーテボリのロレンスベリ劇場で演出家ペール・リンドベリとの共同作業で、シェークスピアやストリンドベリ、タゴールの戯曲に付曲した。特にシェークスピア;「十二夜」のオペラ化を計画、台本も自分で書き、スケッチも始めていた。 ピアニストとしてはモーツァルトに傾倒していった。また、ヴァイオリニストのアンリ・マルトー(モーツァルト演奏で著名)と演奏旅行し、バッハからドビュッシーまでを共演した(その詳細は→ここを押して)。 多忙な生活で健康を害したらしく、ストックホルムに戻ってからは、はかばかしい活動が無い。
ステーンハンマル年譜を見る 斉諧生お薦めの3曲を見る トップページへ戻る 斉諧生へ御意見・御感想をお寄せください。 |