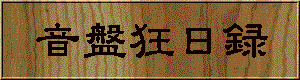|
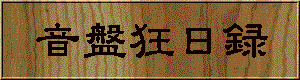
6月30日(日):
 「ボヌ・ノート」レクチャー・コンサート@阿倍野市民学習センターに伺う。テーマは「リリー・ブーランジェの音楽」。 「ボヌ・ノート」レクチャー・コンサート@阿倍野市民学習センターに伺う。テーマは「リリー・ブーランジェの音楽」。
「ボヌ・ノート」はフランス語で「美しい音符」(?)の意、京都フランス歌曲協会で活動している音楽家たちが中心。今回のコンサートを旗揚げに、フランス近現代の佳曲を紹介していきたいとのこと。
メンバーの方から御案内のメールをいただき、リリー・ブーランジェの音楽を実演で聴ける初めての機会に驚喜してお伺いしたもの。
- 今日、演奏された曲目と演奏者は、
- 「春の朝に」・「夜想曲」・「行列」
- 池川章子(Vn) 青谷理子(P)
- 「古い庭で」・「光の庭で」
- 仙波治代(P)
- 歌曲集「空の晴れ間」(抜粋)
- 柚木珠美(Sop) 青谷理子(P)
- というもの。
- (注;邦訳題名は主催者の表記に従う。)
-
- いずれもリリー・ブーランジェの音楽への篤い思いをうかがわせる、心のこもった演奏ばかりで感服した。
- 会場の音響やピアノの状態など、もう少し良い条件であれば…と嘆じざるを得なかったが、完全に手づくりの催しゆえ、それは贅沢な注文というものであろう。
演奏の合間に近藤秀樹氏によるレクチャーがあり、非常に有益な内容であった。
以下、斉諧生が聞き取った範囲で摘録する。言うまでもなく、内容に係る創見は近藤氏のものであり、万一誤り等があれば、斉諧生が文責を負う。
- リリー・ブーランジェは1893年生れ、いわゆる「六人組」(ミヨー、オネゲルら)と同世代になる。1913年、女性として初めてローマ大賞(音楽部門)を受賞した。
- 受賞作「ファウストとヘレネ」は、当時、ドビュッシーがけっこう褒めている。
-
- 彼女の音楽には、フォーレ、ドビュッシーの影響も感じられるが、「若書き・習作」の域をはるかに超越したものである。
- 「春の朝に」は、春めいたスケルツォだが、中間部の切羽詰まった曲調は、死の予感から来るものかもしれない。
-
- 「夜想曲」にはドビュッシーの影響がはっきりしている。
- 特に、曲の終わり近くに出る旋律は「牧神の午後への前奏曲」でFlが吹くメロディに似ている。
-
- 「行列」には、フォーレ;「ドリー」組曲との類似を指摘する人もいるが、自分はドビュッシー;小組曲の第2曲「行列」の方が近いのではないかと考えている。
-
- 「古い庭で」は、グレゴリオ聖歌風のメロディにフォーレ風の和声が付されている。陰のあるメランコリックな雰囲気。
- 「光の庭で」は、サティ・ドビュッシー風。
- この2曲は、あとで述べる、リリーが19世紀末と20世紀の狭間を生きたことの象徴かもしれない。
-
- 歌曲集「空の晴れ間」は、全13曲で演奏時間は30分以上、フランス歌曲の中でも有数の規模の大きさを持つ。
- これを超えるのは、メシアン;「ハラウィ」くらいではないか。
-
- フランシス・ジャムの詩「悲しみ」に付曲したもの。
- ジャムは、19世紀末の象徴主義の複雑な技法等に反発し、率直明快な作風で、人々に受け入れられた。彼の詩を取り上げた作曲家の中では、リリーは早い方である。
-
- 「悲しみ」は失恋を詠った24編の連作。リリーはそのうち13編を取り出し、また詩集全体のタイトルである「空の晴れ間」を曲名とした。
- 恋の喜びや悲しみ、不安と信頼の間を揺れ動く気持ちが良く書けていると思う。
-
- 今日は13曲のうち6曲を取り上げる。音楽の上で節目になっているものを選んだ。
- 第1曲の出だしは、きわめてドビュッシー風。
- 第6曲の半音階的なモチーフは、ワーグナー;「トリスタンとイゾルデ」を連想させる。
- 第12曲は、ドビュッシー;歌曲集「抒情的散文」の第3曲「花」に似ている。
- 第13曲で、詩人は失恋のあと、辛い思い出がある村へ出かけていく。音楽も、既出の旋律を回想するようになっている。特に終わりから5行目で第1曲を引用しているところなど。
- 末尾でリリーは "Plus rien"「何もない…」 を何度も繰り返しているが、これは原詩にない。
- この繰り返しは、失恋の苦しみの中から詩を書くことで再出発する…というジャムの詩の意味を変えてしまうように思う。
- そこにリリーの心情を垣間見るように思うが、どうだろうか。
-
- 共通のモチーフを使って、連作の間に統一感を醸し出している。フォーレなどがよく使った技法である。
- しかしこれは、ヴェルレーヌやマラルメなど、象徴主義の詩によく使われた技法である。
- ジャムの詩がもてはやされるようになったのは第一次世界大戦以降、ミヨーあたりからで、彼らにとってフォーレやドビュッシーは旧時代の作曲家であった。
-
- リリーは、ジャムの詩を取り上げた点で新しいが、音楽語法は19世紀末の古いものであった。
- そこに、二つの世紀の狭間を生きたことが象徴されているのではないか。
-
- しかし、彼女は、そこから更に先へ進んでいった。
- 詩篇三部作の熾烈な音楽は、オネゲル;「ダヴィデ王」を10年先取りしているといえる。
このように素晴らしいレクチャー・コンサートであったが、残念ながら、聴衆の数は多くなかった。
まだまだリリー・ブーランジェという作曲家が認知されていないということであろう。同じようにこのWebpageで紹介していても、ステーンハンマルの方が頂戴するメールが多く、また、実際の演奏機会に恵まれているようだ。
しかしながら、嬉しいニュースが届いた。ジョン・エリオット・ガーディナーが、ブーランジェの作品を録音し、DGGレーベルからリリースされるのである。→ここを押して
察するにストラヴィンスキー;詩篇交響曲のフィルアップに「詩篇」つながりで採用されたということかもしれないが、ともかくメジャー・レーベルがメジャーな演奏家でブーランジェを録音するのは久しぶりといえよう。
このCD発売を機に、彼女の作品が広く聴かれるようになることを期待したい。けっして、近年流行のジェンダー論の文脈でのみ紹介される類の作曲家ではないのである。
 ノルディックサウンド広島からCDが届いた。 ノルディックサウンド広島からCDが届いた。
- カイヤ・サーリケットゥ(Vn) マリタ・ヴィータサロ(P)
- エイナル・エングルンド;Vnソナタ & パーヴォ・ヘイニネン;Vnソナタ(Ondine)
- 北欧音楽MLで話題になったCDである。
- 斉諧生は北欧音楽に強い関心は持っているのだが、ステーンハンマルとシベリウス以外には、なかなか手が回らないのが実情だ。
- とはいえ、「20世紀Vnソナタの名作」「ショスタコーヴィチのVaソナタにそっくり」(以上エングルンド)、「十二音技法がこれ程に有機的に響く例を知らない」(ヘイニネン)等の讃辞を拝読して堪らずオーダーしたもの。
- エングルンドについては、ノルディックサウンド広島のNewsletter No.23を参照されたい。
6月29日(土):
 関西フィルハーモニー管弦楽団第151回定期演奏会@ザ・シンフォニー・ホールを聴く。指揮はジャン・フルネ。 関西フィルハーモニー管弦楽団第151回定期演奏会@ザ・シンフォニー・ホールを聴く。指揮はジャン・フルネ。
- 今日の曲目は、
- オネゲル;交響詩「夏の牧歌」
- ビゼー;交響曲第1番
- ラヴェル;スペイン狂詩曲
- ラヴェル;「ラ・ヴァルス」
- というもの。
-
- 昨年6月、フルネが東京都響を帯同して入洛した折りにはベートーヴェン、ドヴォルザーク、ブラームスというプログラム。それはそれで良かったのだが、やはり本領とすべきはフランス音楽。
- 同じく昨年6月、大阪フィルに客演したときは、ラロ、ファリャ他を指揮したのだが、本業の都合等で聴くことができなかった。
- 今回、関西フィルに上記の曲目で来演するからには聴き逃すべからずと参じたもの。
-
- やはりフルネの声望ゆえか、会場はかなりの入り、ほとんど9割の席は埋まっているように見受けられた。
- また、丁寧なマイクセッティングが行われており、もしかしたらライヴCDが製作されるのかもしれない。
-
- 89歳のフルネ、足取りが少し重そうではあるが、椅子も使わず、最後まで力強い棒さばきを見せていた。
-
- 1曲目、オネゲルの冒頭、静かな弦の伴奏の上にHrnが美しい旋律を吹くのだが、見事にフランス音楽の響きがしているのに驚かされた。
- 中間部のFg、Obなども、ソレらしい音になっている。
- …と書くと関西フィルには失礼か。(^^;
- この団体の実演に接するのは2回目、しかも4年ぶりなので、常日頃の音との違いについては何とも言えない。
-
- 『音楽の友』7月号に掲載されている東京都響の楽員座談会によると、フルネのリハーサルではテンポとリズム、バランスについて厳しく指示があるものの、音については何も言われないという。
- それでいて「えも言われぬ薫りとか空気とかが感じられる」・「振り始めると自然とその曲の音になってしまう」とのことだが、関西フィルでも同様だったのであろうか。
-
- どういう音楽が標題「夏の牧歌」に相応しいのか、日本の我々とスイス人作曲家ないしフランス人指揮者とは受けとめ方が異なるかもしれないが、ともあれ明るく伸びやかな雰囲気は感得することができた。
-
- ビゼーは、全体に落ち着いたテンポで立体的な響き。
- 第2楽章中間部は擬バロック音楽のように響き、また第3楽章など堂々たるメヌエットであった。
-
- 斉諧生的にはもう少し軽やかに、滑るように、走っていってもらいたい…と思わないでもないが、これは曲の捉え方の違いだろう。
- 先日出た東京都響とのCD(Fontec)でも同様のテンポ設定、ただし、音楽は今日の方が更に重かった。
-
- とはいえテンポの弛み、もたれた感じは一切なく、さすがと感じ入った。
- この曲随一の聴きものである、第2楽章の主題を吹くObも佳演。
- ただ、Vn群の高域に音程の幅・音色の硬さが感じられたのは残念だった。
-
- 2曲のラヴェルでは、フルネのコントロールが冴え、さながらスコアの立体彫刻を見るがごとし。大編成のオーケストレーションを生で聴く醍醐味が味わえた。
- スペイン狂詩曲の第2楽章でのコール・アングレも佳演。
- 「ラ・ヴァルス」でワルツ主題の全貌がVaに出るところ、微妙なふくらみが主題に与えられていて、なんとも雅びな雰囲気が漂った。
-
- 全4曲を通じて、きっちりとした高水準の演奏が聴けた喜びはあるが、これで今ひとつ、匂い立つ香気や血の騒ぐ熱狂があれば…と思わずにはいられなかった。
- フルネの音楽は、俗に言う「平凡の非凡」にその本質があると考えている。今回は、その境地まで今一歩、壁を突き抜けられなかったように思う。初顔合わせという事情のゆえであろうか。

- ジョルジュ・エネスコ(指揮) フランス国立放送管 ほか
- バルトーク;弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽 & エネスコ;ルーマニア狂詩曲第2番 ほか(TAHRA)
- エネスコの指揮盤、しかもバルトーク!
- 録音が1951年と古いので、もしかしたらひどい音かもしれないが、バルトークの深い「闇」が聴こえてくることを期待して購入。
- リパッティ;2台Pの協奏交響曲・「ツィガーヌ」第3楽章をカプリング。前者ではマドレーヌ・リパッティとベラ・シキが独奏している。
- これは、前年に早世したディヌ・リパッティの追悼のため。
- 彼の最後の演奏会が1950年9月16日のブザンソン音楽祭でのリサイタルだったことは有名だが、このCDは1951年9月6日のブザンソン音楽祭でのライヴ録音なのである。
- 同じルーマニア出身のエネスコがリパッティ未亡人らを招いて、彼の自作を演奏したわけである。
- 協奏交響曲は1939年の作品で、作曲者とクララ・ハスキルを独奏者として初演されたもの。
- 「ツィガーヌ」は1934年の作品で、実際の演奏会では第2・3楽章が演奏されたとか。
- INAのアルヒーフからの正規音源と表示されており、ちょっと聴いてみたところ、さすがにレンジは狭いものの、歪みや硬さがなく、鑑賞に堪える。
-
- クリスチャン・フェラス(Vn) ボリス・メルソン(指揮) ジュネーヴ・コレギウム・アカデミクム
- 「魔法のヴァイオリン」(DORON)
- 1982年に没したフェラスが、1972年に録音した小品集。この人も聴き逃せないヴァイオリニストになってきたので購入。
- 収録曲は
- ルクレール;タンブーラン
- シューベルト;楽興の時
- ショパン;夜想曲
- チャイコフスキー;憂鬱なセレナード
- ドビュッシー;月の光
- など12曲。一部は指揮者がピアノで伴奏している。
-
- 礒絵里子(Vn) 林俊昭(Vc) 野平一郎(P)
- ベートーヴェン;Pトリオ第7番「大公」・「カカドゥ」変奏曲(LIVE NOTES)
- デュオ・ハヤシでの演奏を愛聴している林さんの新譜が出ていたので購入。
- 彼のCDは全部買うことにしている…と言いたいところだが、カルテット録音は某Vn奏者が苦手なので今のところ避けている(汗)。
- Pが室内楽の名手として知られる野平さん、Vnが新進の礒さんというのも興味を惹かれる。
- 2001年5月の録音。
6月28日(金):
 退勤後、京都府民ホール「アルティ」へ出かける。 退勤後、京都府民ホール「アルティ」へ出かける。
かねて注目しているピアニストエミール・ナウモフを聴くためである。もっとも演奏会の主旨はジャン・フェランディスというフルート奏者のリサイタルであるが…。
- フェランディスはリヨンでマクサンス・ラリューに学び、現在はパリ・エコール・ノルマル高等音楽院で教職にあるとのこと。
- プログラム掲載の略歴には生年が記されていないが、まだ30歳代ではなかろうか。地中海系の好男子である。
-
- 1曲目はモーツァルト;2本のFlとPのためのソナタ K.448。
- もちろんオリジナルではなく、「2台のPのためのソナタ」からの編曲である。賛助出演された瀬尾和紀氏の手になるもの。
-
- 斉諧生は鍵盤楽器には疎く、原曲はろくに知らぬのだが、編曲の不自然さも感じられず、なかなか愉しい音楽だった。
- 問題はフルートの重奏の響きに、最後まで馴染めなかったこと。擦過音が耳について、純正な和声が感じられず、フラストレーションが残った。
- 他の楽器編成で演奏したら、もっと効果が上がるのでは…などと失礼なことを考えてしまった。
-
- 次はフェランディスの無伴奏ソロになって、上林裕子;「廃墟の風」という現代曲(1998年)。
- 京都市響首席の清水信貴が初演したとのこと。
- 題名から考えて、きっと特殊奏法バリバリの、凄まじい響きがするのだろう…と身構えていたのだが、これがまったく勘違い。
- まことに古雅な響きが一貫する、東洋的な「間」の美をあしらった曲だった。
- ドビュッシーか、そのあたりのフランスの作曲家の名前を挙げても納得されてしまいそうな気がした。保守的といえば保守的なのだろうが…。
-
- シューベルト;アルペジオーネ・ソナタは、フェランディス自身が編曲した楽譜による。
- ナウモフがしばし沈思してから弾きだした前奏は、柔らかい夢幻的なピアニシモ。思い入れたっぷりのゆっくりしたテンポだった。
- この響きは、例えばフォーレ;レクイエム(P独奏版)のCDでも聴くことができる、ナウモフの大きな武器。
- これに対して、Flは少し速めのテンポで、あっけらかんと入ってきた。一瞬吃驚。
- もちろんピアニストも即座に合わせた。それ以降のテンポは、おそらくすべてフェランディスのペースだったのではないか。
- 第1楽章展開部でのピアノは予想どおり低音のクレッシェンドを強調、「物凄さ」を演出する。
- ただ、強い音になると響きが詰まり気味で音が硬くなる傾向があった。そのため、時折見せる衝撃的な強奏にも、少し抵抗感がつきまとう。もっと楽器が伸び伸びと鳴らないものだろうか。
- 弱音でのファンタジーが実に豊かなだけに、ちょっと残念、もったいない。
-
- 一方、フェランディスのFlは、音にブレやヨレが皆無、最弱音までピタリと「決まる」鮮やかさ。感心した。
- その点、今年1月に聴いたオリヴィエ・シャルリエのヴァイオリンに似た感じ。
- ちょっとした節回しや表情付けもセンス豊か、味わい深かった。
- 再現部で主題が弱音で出るところでは、素っ気ないテンポと意識的な無表情で、かえって虚無的な気分を表出。心を打たれた。
-
- この曲やフランク;VnソナタがFlで演奏されることを好まぬ斉諧生だが、今夜は率直に、音楽に身も心も浸す感を味わった。
- ナウモフとシューベルト作品集の録音があるそうだ。"La Follia Madrigal"というレーベルから出ているというが、通販サイトを捜したけれど見つからないのは口惜しい。
-
- 後半の最初はルフェーヴル;バルカローレ。
- 作曲者は1843年生・1917年没のフランス人。
- 無名作家の小品ながら、憂愁の趣深い佳曲であった。
- バルカローレすなわち舟歌であるが、舟の揺れるリズム・パターンは聴かれず、むしろ息の長い歌が印象に残っている。
-
- タクタキシュヴィリ;Flソナタ(1968年)もまた佳曲。この曲を聴けて幸運だった。
- いくぶんオリエンタルなムードを湛えた伸びやかな第1楽章、追分馬子歌を連想させる懐かしい旋律がやがて悲愴味を帯びて高揚する第2楽章、リズミカルで愉しいロンドの第3楽章。
-
- 今日のメインともいえる上林裕子;「時の外で」は、今月17日にパリで初演されたばかりの新作、もちろん日本初演とのこと。
- 初演者は今日と同じ、フェランディス、瀬尾、ナウモフの3人。
- 「夜、遠い光」、「踊る光」、「白い光」、「夢の中、回る光」の4曲からなり、概ね「序-急-緩-急」の形式に従う。
- 上記「廃墟の風」同様、聴き易い、情趣のある音楽。
-
- アンコールも3人で、
- ビゼー;「ジプシーの踊り」(歌劇「カルメン」より)
- 上林;「踊る光」
- を。
-
- 結局、ナウモフよりもフェランディスを、またそれ以上に、ルフェーヴルやタクタキシュヴィリを聴いたことが収穫になった。
- この両曲、いずれCDでも聴いてみたいもの。

- イツァーク・パールマン(Vn) アンドレ・プレヴィン(P) ほか
- スコット・ジョプリン;作品集 & アンドレ・プレヴィン;作品集(EMI)
- パールマンのジャズ系LP3枚をCD2枚に収めた廉価盤が出ていたので購入。彼の録音のうち、こうしたジャンルは、今なお他の追随を許さないだろう。
- ジョプリン作品は、パールマン自身の編曲。1974年の録音で、プレヴィンと「イージー・ウィナー」、「ジ・エンターテイナー」など10曲を演奏している。
- プレヴィン作品は、1980年5月録音のアルバム『チョコレート・アプリコット』と同年11月録音のアルバム『イッツ・ア・プリーズ』として発売されていたもの。当時、東芝EMIは「メルティング・サウンド・シリーズ」とか銘打って、これらやステファン・グラッペリなどを売りにかかっていた。
- 各8曲、すべてプレヴィンの書き下ろし。シェリー・マン(Perc)、ジム・ホール(G)、レッド・ミッチェル(Cb)と、ジャズの大家が共演している。
6月26日(水):

- アフラートゥス五重奏団
- モーツァルト;歌劇「魔笛」序曲・ディヴェルティメント ほか(Supraphon)
- 2003年からベルリン・フィルの首席Hrn奏者に就任するというラデク・バボラクを擁する木管五重奏団の新譜が出ていた。
- バボラクには、サイトウ・キネン・オーケストラのマーラー;交響曲第9番のステージで驚嘆しており、この五重奏団での録音も気になっていたところ。
- これまでリリースされたCDは、曲目があまり一般的でなく手を出しそびれていたが、今度のはモーツァルト、しかも「魔笛」序曲が含まれているので飛びついて購入。
- 収録曲は、
- 歌劇「魔笛」・「フィガロの結婚」各序曲
- ディヴェルティメントK.253・K.270
- 自動OrgのためのアダージョとアレグロK.594・幻想曲K.608・アンダンテK.616
- なお、ジャケット等には「フィガロ」序曲の演奏時間が「12分31秒」と記載されているが、これは誤植。CDプレーヤーでは4分17秒と表示されている。
6月25日(火):

- レオポルト・ストコフスキー(指揮) 彼の交響楽団
- チャイコフスキー;交響曲第5番&組曲「胡桃割人形」(BMG)
- 去る4月に覆刻された国内盤CD。
- 両曲ともストコフスキー十八番のレパートリー、いずれも1950年代前半のモノラル録音で、交響曲は3回中2つめ、組曲は4回中3つめのスタジオ盤になる。
- オーケストラは臨時編成の小規模なものながら(弦楽は8-6-4-4-2)、ニューヨーク・フィル、NBC響、フリーランスの名人上手をピックアップしていたという。
- 発売情報に接したときから気になってはいたのだが、『レコード芸術』7月号における宇野功芳師の絶讃を読むに及んで、聴かざるべからずと購入したもの。
- 曰く、
- 「もはや、これ以上の名演は期待し得ないほどの水準(中略)
- <アラビアの踊り>の妖しさは言語に絶する。とろけるポルタメントとエキゾティックなトーン。魔界へ連れ去られること必定だ。」
- なお、ブックレットの裏表紙は、組曲初出時のものらしいLPジャケットだが、これが実に美しい。架蔵に当たって、こちらを表にしておくことにした。
6月24日(月):

- ヘレン・ヤーレン(Ob) ペーター・ツァバ(指揮) ムジカ・ヴィタエ
- モーツァルト;Ob協 & J.C.バッハ;Ob協 ほか(CAPRICE)
- 北欧の弦楽アンサンブルで注目しているムジカ・ヴィタエの新譜が出ていたので購入。
- ソリストはハインツ・ホリガーの弟子で、現在はデンマーク・オデンセのカール・ニールセン音楽アカデミーの教授とのこと。
- 定番モーツァルトのハ長調に、クリスチャン・バッハを2曲、更にフェルレンディスという人の作品を収めているところが目新しい。
- フェルレンディスはイタリア生れ、ザルツブルクのオーケストラでObを吹いており、モーツァルトのK.314は、この人のために作曲された。
- モーツァルトのスタイルで書かれた、魅力的でフレッシュな音楽だという。楽しみである。
6月23日(日):
 ひさしぶりに大量購入(汗)。 ひさしぶりに大量購入(汗)。
- ユベール・スダーン(指揮) ザルツブルク・モーツァルテウム管
- モーツァルト;交響曲第34・39番 ほか(Arte Nova)
- 東京交響楽団への来演(しかもブルックナー;交響曲第0番!)で注目されるスダーン。
- 先月の京都公演は本業と重なったため聴き逃したが、モーツァルト;交響曲シリーズ第1弾というCDが店頭に並んでいたので購入。
- Arte Novaには珍しくブックレットにオーケストラのメンバー表が掲載されており、それによれば弦合奏は8-6-5-4-2の編成だったことになる。
- メヌエット ハ長調 K.409をフィルアップ。
- 2002年1月、モーツァルテウム・大ホールでの録音。
-
- スタニスラフ・スクロヴァチェフスキ(指揮) NHK響
- ベートーヴェン;交響曲第5番&ルトスワフスキ;管弦楽のための協奏曲 ほか(Altus)
- スクロヴァチェフスキの新譜が4点同時に登場、嬉しい悲鳴を上げながら購入(苦笑)。
- その昔のハレ管とのブラームス;交響曲全集(IMP、最近再発された)やウェーバー;序曲集(IMP)で注目し、ミネソタ管とのブルックナー;交響曲第9番(Reference Recordings)に随喜の涙を流して以来、ずっと買ってきた指揮者である。
- マイナー好きの斉諧生としては、彼が「知る人ぞ知る」存在でいてくれた方が有り難いような気分もしないわけではないが、このように実演を聴けなかった録音が発売されるのは、やはり嬉しい。
- 1999年1〜2月に来演したときの記録で、標記ベートーヴェンは2月5日のNHKホール、ルトスワフスキは1月27日のサントリー・ホールでのライヴ録音である。
- 後者と同時に演奏されたベートーヴェン;大フーガ(ワインガルトナーによる弦楽合奏版)をフィルアップ。
-
- スタニスラフ・スクロヴァチェフスキ(指揮) NHK響
- モーツァルト;交響曲第29番&シューマン;交響曲第4番(Altus)
- 1996年2月8日、NHKホールでのライヴ録音。
- スクロヴァチェフスキは作曲家でもあり、近現代作品を得意にしている。米VOXにラヴェル、バルトーク、ストラヴィンスキーの主要管弦楽曲を網羅的に録音しているほどだ。
- それと同時に、独墺系ロマン派の楽曲で中欧系の渋い素晴らしい響きを聴かせてくれる(上記ウェーバーが好例)。
- それゆえ、特にシューマンに期待したい。
-
- スタニスラフ・スクロヴァチェフスキ(指揮) NHK響
- ブルックナー;交響曲第7番(Altus)
- 上記のように、スクロヴァチェフスキの讃仰者となる最大の契機になったのはブルックナー;交響曲第9番(Reference Recordings)の録音であった。
- もちろんArte Novaからは全集も出ているが、更にN響とのライヴが登場するというのは大歓迎である。
- 1999年1月21日、NHKホールでのライヴ録音。
- 今年9月には読売日響と第8番との演奏会が予定されている。
- あまりの好評に追加公演まで組まれているとのこと、都合がつけば聴きに参じたいものだが、はてさて…。
-
- スタニスラフ・スクロヴァチェフスキ(指揮) NHK響
- チャイコフスキー;交響曲第5番&ベートーヴェン;「レオノーレ」序曲第2番(Altus)
- スクロヴァチェフスキが最初に日本の聴衆の前に姿を現したのは、N響ではなく読売日響で、その時に指揮したのが、このチャイコフスキーの曲だったと、たしか藤田由之氏の文章で読んだことがある。
- 実に精緻に設計された音楽だったが当時の日本の聴衆には受け入れられなかったようだ…と書いておられたように記憶するが、残念ながら現物が出てこない。ずいぶん以前の『音楽現代』誌だったと思う。
- N響との本格的な共演としては初めての定期シリーズで、この曲を取り上げたのも、指揮者に自負するところがあるのだろうか。期待して聴きたい。
- 1996年2月2・3日の録音とのみ記されている。なお、ライナーノートによれば、チャイコフスキーのフィナーレでポケットベル音が聞こえるらしい。
-
- カルロス・クライバー(指揮) ウィーン・フィル
- 「ニューイヤー・コンサート 1989」(Sony Classical)
- クライバーが初めてニューイヤー・コンサートを指揮した際の実況盤、いわずとしれた大名盤である。
- 恥を忍んで告白するが、実は、これまで買ったことがなかった(激汗)。
- たしかTV中継は見ていたのだが、ちょうど音盤から遠ざかっていた時期に当たり、買い損ねたまま、ずっと来たのである。
- いつしかクライバーも(ほとんど)過去の人となり、この2枚組も店頭で見ることは少なくなってしまった(ハイライト盤は残っていると思うが)。
- 今日、偶々、中古盤コーナーで格安のものを見つけ、今のうちにと購入した次第。
-
- エリック・ヘープリッチ(Cl) フランス・ブリュッヘン(指揮) 18世紀管 ほか
- モーツアルト;Cl協 ほか(GLOSSA)
- 一頃は向かうところ敵なしがごとき勢いだったブリュッヘン&18世紀管の音盤も、ずいぶん寂しくなってきた。
- 1990年に聴いた実演の「田園」と「リンツ」の感激は今でも忘れられないので、彼らの新譜は買わざるべからず。
- 音源の構成が、ちょっとややこしい。
- Cl協(2001年2月、オランダ・ハーレム)
- 歌劇「皇帝ティトゥスの慈悲」序曲(1986年6月、オランダ・ニーメゲン)
- 同、アリア2曲(2001年11月、オランダ・アムステルダム)
- アダージョ K.411(2001年12月、オランダ・フェーネンダル)
- フリーメーソンの葬送行進曲(1998年3月、東京芸術劇場)
- となっている。
- なお、最後の東京録音は、以前、レクイエムにフィルアップされて発売されていたものと同一で、ちょっとがっかり。
-
- ウィーン室内合奏団
- モーツァルト;室内楽曲集(ART UNION)
- 1970年前後にトリオが日本で録音した音源をCD化した3枚組。
- 一部は中古盤LPで架蔵しており、できればそれで揃えたいのだが、なかなか難しそうなので、今日立ち寄った音盤屋で見かけたついでに購入。
- 何といっても、ヴァルター・ヴェラーやゲルハルト・ヘッツェルが第1Vnに座っているところが値打ちである。
- セレナード第13番 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」(ヴェラー、1969年2月25日、埼玉会館、以下同じ)
- 弦楽五重奏曲第3番(ヴェラー)
- ディヴェルティメント K.136(ヴェラー)
- Cl五重奏曲(ヴェラー、アルフレート・プリンツ(Cl))
- Fl四重奏曲第1・4番(ヘッツェル、ヴェルナー・トリップ(Fl)、1971年7月9日、川口市民会館、以下同じ)
- 弦楽四重奏曲第14・19番(ヘッツェル)
- もちろんそれ以外の奏者も、ヴィルヘルム・ヒューブナー(第2Vn)、ルドルフ・シュトレンク(Va)、ロベルト・シャイヴァイン(Vc、ヴェラー盤)、アーダルベルト・スコチッチ(Vc、ヘッツェル盤)、ブルクハルト・クロイトラー(Cb)と、一騎当千の名人上手達。
- ブックレットに掲載されているプロデューサー中野雄氏の回想によれば、いずれもほとんどテイク・ワン限りの一発勝負であったとか。
- どの演奏からも暖かい音色がたちのぼり、若林駿介氏の手になる録音の素晴らしさを伺わせるが、マスターテープの劣化も垣間見え、やはりオリジナルのLPを入手したいものである。
-
- 久保田巧(Vn) アヴォ・クユムジャン(P)
- シューベルト;幻想曲 ほか(日本CROWN)
- 標記作品は、数あるヴァイオリン曲の中でも愛惜ひときわ。
- 久保田さんは以前買ったバッハ(JOD)が良かったので、この1995年録音盤も買おう買おうと思っていたもの。
- 彼女は先頃亡くなったヴォルフガング・シュナイダーハンに学んだとか。直伝のシューベルトに期待したい。
- 二重奏曲 D.574とロンド D.895をカプリング。
-
- コンスタンティン・クルカ(Vn) ほか
- ヴィエニャフスキ;ヴァイオリン作品集(CD accord)
- CD2枚組に、ヴィエニャフスキのVn独奏曲を集成したアルバム。
- 最初に見かけたときには、おそらく落ち穂拾いの無名曲集と(勝手に)断じ、手を出さなかった。
- ところが『レコード芸術』7月号では濱田滋郎・那須田務両氏とも、あるいは佳曲、あるいは秀演と厚い讃辞を呈しておられる。
- これはヴァイオリン音楽ファンとしては聴かざるべからずと購入したもの。
- 日本語帯・解説付き国内盤仕様のものは3,570円だが、店頭で見つけた輸入盤は2,700円ほどで、ちょっと得をした気分(笑)。
-
- マリオ・ブルネロ(Vc) アンドレア・ルケシーニ(P)
- ブラームス;Vcソナタ第1・2番(VICTOR)
- 一般的な知名度はないが、その筋には隠れもない名手ブルネロの新譜が国内盤で出ると聞いて、いてもたってもいられず、買いに走った(今日の音盤屋廻りの第1目標)。
- まずブラームス。
- バッハ;無伴奏とベートーヴェン;ソナタ全集は既に伊AGOLAレーベルから出ているから、これは価値のある企画だ。
- ピアニストはベートーヴェンでも共演していた人である。
- 1999年8月、イタリア・シエナでの録音。
-
- マリオ・ブルネロ(Vc)
- カサド;無伴奏Vc組曲 ほか(VICTOR)
- ブルネロの新譜もう1点は無伴奏アルバム。標記の有名なカサド作品以外に
- ソッリマ;アローン(1999年)
- リゲティ;無伴奏Vcソナタ(1953年)
- ダラピッコラ;シャコンヌ、間奏曲とアダージョ(1945年)
- イザイ;無伴奏Vcソナタ(1925年)
- を収めている。とりわけリゲティとダラピッコラには注目したい。
- イザイ作品のみ2002年4月、それ以外は1999年7月のイタリア録音。
-
- イルジー・バールタ(Vc) マリアン・ラプシャンスキー(P)
- ラフマニノフ;Vcソナタ&シュニトケ;Vcソナタ&ペルト;フラトレス(Supraphon)
- このチェリストにはバッハ;無伴奏をはじめ、多数の録音があり、ずっと気になっていた。
- 今日、音盤屋の棚をあれこれ見ていると、標記の魅力的なプログラムの盤があり、これで好みに合う人かどうか試してみようと購入。
- チェロ独奏による「フラトレス」の録音は珍しいのではないか。
-
- アレックス・ヤコボヴィッツ(Perc)
- マリンバ作品集(Arte Nova)
- これは『レコード芸術』7月号の「海外盤試聴記」で興味を惹かれた1枚。
- 評者は吉村渓氏、曰く
- 「アルテ・ノヴァが、また面白い才能を発掘してくれた。(中略)妖しいまでの吸引力は、果たして何と形容すればいいのか……」
- それが大阪の音盤屋に600円弱で並べられていたのを見つけ、思わず購入。
- 無慮14曲を収めるが、面白そうなものを挙げれば、
- バッハ;シャコンヌ(無伴奏Vnパルティータ第2番より)
- ベートーヴェン;アダージョ・ソステヌート(Pソナタ「月光」より)
- ムソルグスキー;「古城」(「展覧会の絵」より)
- タレガ;アルハンブラの思い出
- サティ;ジムノペディ第1番
- といったところ。
-
- パオロ・パンドルフォ(Gamb) ほか
- マレ;組曲集・「スペインのフォリア」(GLOSSA)
- バッハ;Gambソナタの名演(HMF)以来、気にかけているパンドルフォ。
- 次々に新譜を出しているのでフォローし切れていないのだが、マレの名曲「スペインのフォリア」の名演を聴かせているというので購入。
- この曲を印象的に使った映画「めぐり逢う朝」は、斉諧生も見に行ったものだ。
- もっともフォリアはボーナスCDで、メインは組曲3曲を収めた1枚。
6月22日(土):
 Alapage.comからCDが届いた。 Alapage.comからCDが届いた。
- フランソワ・ルルー(Ob) パスカル・モラゲス(Cl) シュテファン・ザンデルリンク(指揮) ブルターニュ管
- モーツァルト;Ob協K.314・Cl協 ほか(Pierre Verany)
- 先月、大阪センチュリー響との演奏を聴いたルルーのCDを検索してみたら、未架蔵のものが見つかったのでオーダーしたもの。
- Clの俊秀モラゲスとカプリングされている上、指揮がかねて評価しているザンデルリンクの息子(弟のほう)というのは嬉しい限り。
- 更に偽作とされているOb協変ホ長調KV Anhang 294bをカプリング(この曲については、少し調べてみたものの詳細不明)。
- 2000年9月の録音。
-
- フランソワ・ルルー(イングリッシュ・ホルン) ジャンヌ・トムゼン(Fl) ローラン・クェネル(指揮、Vn) ヨーロッパ・カメラータ
- オネゲル;Flとイングリッシュ・ホルンのための室内協奏曲&ショスタコーヴィッチ;室内交響曲op.110a ほか(Syrius)
- ↑と同じくルルーの未架蔵盤をオーダー。
- オネゲルの曲は、先だってフルネ&群馬響盤も出たが(ALM)、比較的珍しい作品である。
- 蒐集しているショスタコーヴィッチのop.110aが入っていたのも嬉しい限り。
- 更にオネゲル;バッハの名前に基づくプレリュード、アリオーソとフゲッタとショスタコーヴィッチ;前奏曲とスケルツォを演奏している。
- ヨーロッパ・カメラータは、EUユース管の出身者からなるアンサンブルで、クェネルがコンサートマスターと音楽監督を兼ねているとのこと。
- なお、ショスタコーヴィッチといえば、いつもの工藤さんのページ。
- op.11については「抒情的な美しさに重点をおいた解釈で、(中略)これはこれで作品の真価を適正に伝える演奏である。」と星4つ半。
- op.110aについては「真摯で正攻法の演奏。(中略)これといったセールスポイントに欠ける。」と星4つの評価である。
- 1998年録音。
-
- トーマス・ヘンゲルブロック(指揮) フライブルク・バロック管 ほか
- バッハ;ロ短調ミサ(DHM)
- 許光俊&鈴木淳史『クラシックCD名盤バトル』(洋泉社)で紹介されていた盤である。
- これは鈴木淳史氏の推奨盤で、
- 「オリジナル楽器にありがちな急造プレハブみたいな安っぽさがない。(中略)器楽のイキイキ感にも事欠かない。何よりもリズム感がよく、最終曲の合唱も堂々としたものだ。」
- と珍しく(?)素直な評文なので気になっていたのである。
- 店頭でも見かけるのだが、フルプライス2枚組で買いそびれていたところ、Alapage.comでは25.33ユーロ(3,000円弱)と安価だったのでオーダーしてみた。
- 1996年10月録音。
6月20日(木): 5月30日、高関健のブルックナー;交響曲第4番の項に次のように書いた。
まず、ハース版使用というのが目を惹く。近年もっぱらノヴァーク版が行われている中、この版は近年入手すら困難になりつつある。
これについて読者の方からメールを頂戴した。第4番(と第7番)に関しては、Dover社の大判廉価スコアで入手可能とのことである。
そういえば、斉諧生も楽譜店で見かけたことがある。あれがハース版とは気づいていなかった(汗)。
また、時々利用するSheet Music Plusを "Bruckner&Haas" で検索してみると、Kalmus社のものも入手できるようだ。
上の記事を書いたときには旧東独の Breitkopf & Härtel 版だけを思い浮かべていた。訂正するとともに、御教示に感謝を申し上げたい。
6月18日(火):

- 齋藤秀雄(指揮) 日本フィル
- ベートーヴェン;交響曲第5番&チャイコフスキー;弦楽セレナード(EXTON、DVD)
- 斎藤秀雄は教育者として有名だが、彼が指揮したディヴェルティメントK.136など見事な辛口のモーツァルトで(東芝EMI)、演奏家としても見過ごせない人だと考えている。
- その指揮映像がDVDで出たので購入。このところEXTONから出ている旧・日本フィルの映像資料は、本当に貴重なものばかりだ。
- ベートーヴェンは1969年9月16日、チャイコフスキーは1968年9月30日、いずれも東京文化会館での定期演奏会のライヴ。
- 映像はともに白黒だが、音声はベートーヴェンがステレオ、チャイコフスキーはモノラル。もっとも状態は非常に良好である。
- ベートーヴェンを視聴してみた。
- もちろん棒は極めて明晰だが、指揮姿全体からはむしろ無骨な印象を受ける。
- 演奏も、ノイエ・ザッハリヒカイト全盛期のドイツに学んだ人らしい端正さの中に、時折、少し古風な粘りも見えて、なかなか味わい深い。
-
- イヴリー・ギトリス(Vn)
- 「ヴァイオリンの至芸」(東芝EMI、DVD)
- かつてLDで出た時に買いそびれた、来日時のカザルス・ホールにおける無伴奏リサイタル(1990年7月30日)の映像記録がDVDで出直したので購入。この「ヴァイオリンの怪人」の姿は見逃せない。
- 収録曲は
- バッハ;シャコンヌ(無伴奏Vnパルティータ第2番より)
- バルトーク;無伴奏Vnソナタ
- バッハ;フーガ(無伴奏Vnソナタ第3番より)
- 即興演奏(成田為三;浜辺の歌による)
- バッハ;ガヴォット(無伴奏Vnパルティータ第3番より)
- というもの。
- このうちバッハのソナタ第3番は、実際のコンサートでは全曲演奏されたという。DVDでは収録時間を60分に収める必要はないのだから、なんとも惜しいことである。
6月17日(月):

- クリスチャン・テツラフ(Vn) タベア・ツィンマーマン(Va) ターニャ・テツラフ(Vc) ほか
- モーツァルト;ディヴェルティメント K.563 ほか(EMI)
- テツラフの新譜2点が出ていたので購入。いずれも「シュパヌンゲン;ハイムバッハ室内楽音楽祭」のライヴCDである(音楽祭の公式Webpageは→ここを押して)。
- この音楽祭は、ハイムバッハの水力発電所(1904年築造の、美しいアール・ヌーヴォー様式の建物)で行われるもので、既に1999年・2000年のライヴCDが出ている。
- 今回のリリースは、2001年6月15〜24日に行われた昨年の音楽祭からの収録。これまでは2枚組だったが、こんどはバラで登場。
- 1枚目でのテツラフの演奏は標記のモーツァルトだけで、それ以外には
- ラルス・フォークト(P)アンテ・ヴァイトハース(Vn)アルバン・ゲルハルト(Vc)
- ハイドン;P三重奏曲ハ長調 XV27
- ダグ・イェンセン(Fg)ターニャ・テツラフ(Vc)
- モーツァルト;Fg&Vcソナタ K.297
- を収めている。
-
- クリスチャン・テツラフ(Vn) ディームト・シュナイダー(Cl) ラルス・フォークト(P) ほか
- ヒンデミット;無伴奏Vnソナタ&ベルク;アダージョ ほか(EMI)
- テツラフのハイムバッハ・ライヴ、続く。
- 1枚目はウィーン古典派だったが2枚目は20世紀の音楽で固められている。
- ヒンデミットの無伴奏作品はop.11-6、若い頃の作品で(1917〜18年)、「完全版による初演」と注記されている。
- ベルクは「室内協奏曲」の第2楽章を作曲者自身がVn・Cl・Pに編曲したものとのこと。
- この2曲以外には、
- ヒンデミット;10楽器のためのソナタ(断章)(1917年、初演)
- プーランク;Ob・Fg・P三重奏曲
- プロコフィエフ;Ob・Cl・Vn・Va・Cb五重奏曲
- を収録、いずれもテツラフは参加していない。
-
- アディリア・アリーヴァ(P) オルティス四重奏団
- マルタン;P五重奏曲&ブロッホ;P五重奏曲 ほか(CASCAVELLE)
- フランク、フォーレは言わずもがな、ヴィエルヌやマニャール、フローラン・シュミット等まで、P五重奏曲は好きな曲種。
- マルタンも好きな作曲家なのだが、この曲はチェックしていなかった。静謐な音楽美を期待して購入。
- 更にマルタンより6歳年下のスイスの作曲家マルク・ブリケ(Marc Briquet)の同種曲をカプリング。
- ピアニストはロシア出身(ギンズブルクの弟子とか)、四重奏団はジュネーヴの団体とのこと。
-
- ヴァレリー・エマール(Vc) セドリック・ティベルギアン(P)
- ヴィエルヌ;Vcソナタ&オネゲル;Vcソナタ&ドビュッシー;Vcソナタ ほか(LYRINX)
- ↑五重奏曲で名前を出したヴィエルヌ、VcソナタのCDが出ていたので購入。
- オネゲルの作品やショーソン;VcとPの小品が含まれているのも嬉しい。
- エマールは1969年リヨン生まれ、パリ音楽院でフィリップ・ミュレらに、またバーナード・グリーンハウスに学んだとのこと。
6月16日(日): 以前(平成12年10月)、Vesselin Paraschkevovというヴァイオリニストのバッハ;無伴奏Vnソナタとパルティータの全曲盤を入手した(TELOS)。
その折りに「読み方がよくわからない」とか、「1973〜75年にウィーン・フィルのコンサートマスターだったというが、聞いたことがない」とか、いくぶん無礼なことも書いていたところ、姻戚に当たられる方からメールを頂戴した(御令室どうしが姉妹でいらっしゃるとのこと)。
御教示によれば、名前は「ヴェッセリン・パラシュケフォフ」、経歴にも間違いはないそうである。失礼をお詫びしたい。m(_ _)m
このヴァイオリニストが、来月、神戸で無伴奏リサイタルを開くという情報を得た。→ここを押して
バッハ、バルトーク、イザイという曲目も魅力的。できれば聴きに参じたいものである。
6月13日(木):

- クラウディオ・アバド(指揮)ベルリン・フィル
- マーラー;交響曲第9番(DGG)
- 国内盤が先行発売されていたアバドのマーラー;第9交響曲の輸入盤が並んでいたので購入。
- この作品、いまや斉諧生にとって買い逃せない曲になりつつある。
- 先だってClassical CD Information & Reviewsで高い評価が与えられていたのも記憶に新しい。
6月11日(火):

- ネヴィル・マリナー(指揮)カダケス管
- アリアーガ;交響曲 ほか(TRITO)
- 愛惜佳曲書に掲げたアリアーガの佳品の新譜を見つけたので、断然購入。
- スペインのオーケストラをマリナーが振っているというのが珍しい。
- ブックレットの記述がスペイン語だけなので詳細は不明だが、表紙の写真からすると、かなり小型の室内管のようだ。
- 同じ作曲家の歌劇「幸福な奴隷」序曲をフィルアップ、1996年1月22日の録音。
-
- イーゴリ・マルケヴィッチ(指揮)日本フィル
- プロコフィエフ;交響曲第1番&ファリャ;「三角帽子」第2組曲 ほか(東芝EMI)
- 新譜予告でチラッと見て、学研から出たライヴ盤の再発と思いこんでいた。
- 店頭でふと東芝のチラシが目にとまり、読んでみるとスタジオ録音とのこと。驚愕して直ちに指揮者別の棚に走り、無事確保した。
- 標記2曲以外に
- デュカス;交響詩「魔法使いの弟子」
- ラヴェル;「ラ・ヴァルス」
- をカプリングし、デュカスは30分ほどのリハーサル風景も収録されている。
- これらは、4回目の来日に当たる1970年、5月18〜20日に世田谷区民会館で録音されたもの。
- この年の実演では、メンデルスゾーン;交響曲第4番、チャイコフスキー;幻想序曲「ロメオとジュリエット」、ファリャ;「三角帽子」組曲を取り上げており、これらは学研(のちPLATZ)からCD化されていた。
- また、プロコフィエフとラヴェルは1968年の3回目の来日時に演奏しており、同様に学研(PLATZ)盤に収録されている。
- いずれの曲もマルケヴィッチの十八番といえるもので、フィルハーモニア管などとのスタジオ録音もあった。
-
- マーカス・クリード(指揮)RIAS室内合唱団
- ブリテン;「神聖と世俗」&ディーリアス;2つの無伴奏パート・ソング ほか(HMF)
- 大好きなディーリアス作品、演奏時間4分半ほどとはいえ買わざるべからず。(なお、この曲をエリック・フェンビーが弦楽合奏にアレンジしたのが「二つの水彩画」。)
- 特に合唱団は、以前のプーランク・アルバムが中古音盤堂奥座敷で高い評価を得た団体。ドイツ人のイギリス音楽は敬遠気味の斉諧生といえども見逃すことはできない。
- 録音が比較的珍しい標記ブリテン作品に加え、
- ブリテン;聖セシリア讃歌
- ヴォーン・ウィリアムズ;3つのシェークスピア歌曲
- エルガー;パート・ソング(3曲)
- スタンフォード;「青い鳥」
- を収録。
6月10日(月):

- リッカルド・シャイー(指揮)コンセルトヘボウ管
- ブルックナー;交響曲第8番(DECCA)
- シャイーは最近、さほど買っていない指揮者だが、ブルックナー;第8が出たからには購入せざるべからず。
- ノヴァーク版使用、1999年5月録音。
-
- オスモ・ヴァンスカ(指揮)ラハティ響
- シベリウス;管弦楽曲集(BIS)
- ヤルヴィに替わってシベリウスの交響曲・管弦楽曲大全集を録音しようかというヴァンスカ、未録音だった比較的ポピュラーな管弦楽曲を一斉にリリースした。
- 主な収録曲は、「エン・サガ」、「ポヒョラの娘」、「夜の騎行と日の出」、「吟遊詩人」、「大洋女神」。
- 「エン・サガ」は既に1892年版(初稿)を録音していたが、今回は通用の1902年版。
- 更に比較的録音が珍しいop.45の2曲、「木の精」と「ダンス・インテルメッツォ」を収録している。
6月9日(日): このところ本業多忙で音盤屋廻りもままならぬ有様、更新も遅れてしまって申し訳ありません。
 5月30日のコンサートを演奏会出没表に追加。 5月30日のコンサートを演奏会出没表に追加。
また、音盤狂昔録に平成14年5月分を追加。
6月4日(火):

- ゲルハルト・ボッセ(指揮)アンサンブル
- ベートーヴェン;交響曲第1番 ほか(アフィニス文化財団)
- JT(日本たばこ)系のアフィニス文化財団が開催している「アフィニス夏の音楽祭」の記録CD。またまた財団のWebpageから「CDプレゼント」に申し込んだもの。
- いつも情報を頂戴しているWOODMANさんのユビュ王の食卓さんの掲示板で、このベートーヴェンがボッセ氏の指揮であることがわかり、あわてて応募した。
- アンドレアス・レーン(@バイエルン放送響コンサートマスター)、四方恭子(@ケルン放送響コンサートミストレス)ら、講師陣も加わっての演奏である。
- カプリングは、
- ボッケリーニ;弦楽五重奏曲 ハ短調 op.37-1
- ヤナーチェク;管楽六重奏曲「青春」
- ショスタコーヴィチ;弦楽八重奏のための2つの小品 op.11
平成14年5月25日(土):黄金週間中のウィーン旅行の顛末を「維納旅行記」として公開。
平成13年2月3日(土):ドメイン"www.seikaisei.com"を取得しサーバーを移転。「音盤狂日録」の過去ログを「音盤狂昔録」として公開。
平成12年9月10日(日):「提琴列伝」に、ミクローシュ・ペレーニを掲載。
平成12年1月8日(土): バッハ;無伴奏Vc組曲聴き比べを掲載。
平成11年10月24日(日): ラハティ交響楽団シベリウス・チクルス特集を掲載。
平成11年8月28日(土): 「逸匠列伝」にカール・フォン・ガラグリを掲載。
平成11年5月9日(日): 「作曲世家」にリリー・ブーランジェを追加。
平成10年5月5日(祝): 「作曲世家」にステーンハンマルを掲載。
平成10年2月8日(日): 「逸匠列伝」にルネ・レイボヴィッツを掲載。
平成9年11月24日(休): 「名匠列伝」に、アンゲルブレシュトを追加。
平成9年9月15日(祝): 「畸匠列伝」に、マルケヴィッチを掲載。
平成9年8月24日(日): 「名匠列伝」にカザルスを追加。
平成9年8月8日(金): 『斉諧生音盤志』を公開。
音盤狂昔録へ戻る
トップページへ戻る
斉諧生に御意見・御感想をお寄せください。
|